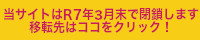鹿児島県川辺出身。鹿児島県川辺郡で議員を務めていた高良善十郎・登美(共に同墓)の子。兄に耐火物技術研究者の高良淳(同墓)がいる。甥で耐火煉瓦研究者の高良義郎(同墓)。
1924(T13)九州帝国大学医学部卒業。同大学精神神経科講師を務めている時に、同大学精神科の研究員の とみ(同墓)と知り合い付き合いが始まる。とみが同大学の助教授に推薦されるが、美濃部達吉(25-1-24-1)の「未婚の女性が男子学生に教えるなんてとんでもない」との反対で大学を去り、'27(S2)母校の日本女子大学教授となる。これをきかっけに、'29武久も同大学を去り、東京慈恵会医科大学に転任し、同年二人は東京で結婚した。同時期に東京根岸病院に勤務し、森田正馬に師事して「森田療法」を継承。'37森田の後を継いで東京慈恵会医科大学教授に就任した。
'40東京都新宿区中落合に、森田入院療法の施設として高良興生院を設立。森田療法による神経(質)症の治療を行う。戦争により一部を焼失したが、戦後も治療者と患者が起居をともにする家庭的森田療法の原型を守る病院として診療を続けた。また森田療法を学ぶ医師たちのために、研修の場として開放するなど後進の指導も行った。'64東京慈恵会医科大学名誉教授。
主な著書に『性格学』(1931)、『神経質並に神経衰弱の性格治療』(1933)、『子供の精神衛生』(1942)、『人間の性格』(1943)、『対人恐怖の直し方』(共著:1952)、『赤面恐怖の治し方』(共著: 1953)、『ノイローゼの徹底療法』(1964)、『生きる知恵〜神経質を活かす正しい生活道〜』(1972)、『森田精神療法の実際〜あるがままの人間学〜』(1976)、『どう生きるか〜神経質を活かす秘訣〜』(1978)、『精神医学者の随想』(1983)、『高良武久著作集 全6巻』(1988)がある。
享年97歳。没後、高良興生院は閉鎖となり、高良興生院の跡地の一部が、高田馬場で精神障害者の支援に取り組んできた「かがやき会」に寄贈、2000(H12)精神障害者の就労センター「街」が建設され活動が開始された。この建物の一部に記念室をもうけ「高良武久・森田療法関連資料保存会」が発足。
1999(H11)娘で詩人の高良留美子(次女)と画家の高良眞木(長女:同墓)が編集し『高良武久詩集』を刊行。また、2013岸見勇美の著作『高良武久森田療法完成への道〜不安な時代に生きる知恵〜』の伝記が刊行された。
<「高良武久・森田療法関連資料保存会」の紹介文など>
【森田療法】
森田療法とは、東京慈恵会医科大学の初代精神科教授・森田正馬(もりたまさたけ/しょうま・1874-1938)が創始した精神療法で、1919(T8)に確立された。対人恐怖や広場恐怖などの恐怖症、強迫神経症、不安神経症(パニック障害、全般性不安障害)、心気症などが主たる治療の対象であり、これまでに高い治療効果をあげてきている。
森田はフロイトと同時代人であり、この心理学の黎明期に、西では精神分析療法、東では森田療法が生み出されたことになる。森田療法は、何かにとらわれて心が流れなくなる状態を、絶対臥褥(7日間気晴らしをせず寝たままでいる)、日記指導、作業、読書などを用いて段階的に打破し、「あるがまま」の健康的・創造的な心的状態へと変化させていく治療法である。原法は家庭的入院療法だったが、現在は入院療法を実施できる施設は少なくなり、外来での森田療法が主流となっている。入院治療ができない場合は日記指導、外来指導、集団指導などを行う。
<高良興生院・森田療法関連資料保存会「森田療法」説明文など>
|