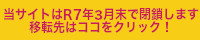水内郡村山村(現長野市)に生まれ幼名を覚太と称し、家督を相続し善之助を襲名。
若くして学問を好み才気にたけ、1878(M11)26歳で戸長、1881年長野県会議員、翌年は上水内郡町村連合会議長に推される。
1883年(M16)更級、埴科の郡長に抜擢、次いで南北安曇郡長に任じられ、積極的に道路の改修と橋梁の架設に務めた。
1889信濃銀行を創立し頭取となり、翌年国会開設に伴い長野県第一区から衆議院議員に当選。以後、1892、94と当選し北信の政財界の第一人者となった。
1897京都の疎水発電所と並んでわが国最初の電灯事業に着手し、長野電灯会社を創立して茂菅発電所を建設、社長となった。
翌年には岡本孝平から信濃毎日新聞社を譲り受け、主筆に山路愛山を招き「社長といえども紙面に干渉せず」と編集の独立を宣言し近代化を図った。1902政友会に入党、4度目の衆議院議員に当選した。
伊藤博文や松方正義らとも親交が深く、長野県知事や日本勧業銀行副総裁の招請もあったが、地方産業の振興と郷土文化の育成に専念した。
長男の順造(同墓)も衆議院議員、日本発送電総裁。三男武雄は信毎社長に就任。孫の善太郎(同墓)、徳三郎も衆議院議員として活躍してた政治家一家である。
<日本国会議員名鑑など>
<MATHU様より情報提供>


*墓石正面「小坂氏墓」、裏面は小坂善之助の略歴と、昭和十年八月次子の善次郎没後に多磨墓地に分葬し遺骨を併葬した旨、最後に「昭和十年十一月 小坂順造 撰並建」と刻む。墓所右側に墓誌が建つ。令和3年現在刻まれている名前は右から下記である。初代の小坂善次郎、うた。二代 小坂善之助、きく。三代 小坂善三、こそ。四代 小坂善之助、志げ。五代 従三位 勲一等 小坂順造、花子。小坂善次郎、直、百合子。六代 正三位 勲一等 小坂善太郎。正三位 勲一等 小坂徳三郎、旦子。七代 小坂順之助。小坂憲次。
【小坂家】
小坂家は現在の長野市柳原に江戸時代から居を構える三百石の大庄屋。多磨霊園の墓石には初代 小坂善次郎から代々刻まれている。初代の善次郎は文学と茶を親しむ文化人であった。2代目の小坂善之助の進取の気性は千曲川堤防対策に発揮され、幕末には私財を投じて改修工事に当たり、それが自分に跳ね返って資産を増やした。3代目の小坂善三(後に小坂善之助)は2代目の長女の小坂こそ の婿養子となる。
4代目の小坂善之助が更級、埴科や南北安曇の群長の後、1890(M23)第1回帝国議会の衆議院議員に当選、さらに信濃銀行や長野電灯の創設、信濃新聞創刊と地方王国小坂財閥の礎を築いた。5代目は小坂順造で長男、政治家として活動。次男の義雄は小坂才兵衛の養子。三男の小坂武雄は信濃毎日新聞社長・政治家。長女のちか は政治家の花岡次郎の妻。二女のはる は日本銀行総裁の深井英五の妻。三女の国 は三菱銀行副頭取の関根善作の妻。四女の菊江 は陸軍少将の津野田是重(7-2-14-13)の妻。
6代目は小坂善太郎で長男。次男は善次郎。三男の小坂徳太郎は政治家。長女の百合子は東京都知事の美濃部亮吉(25-1-24-1)に嫁ぐも離婚し戻り、子どもたちは小坂姓となる。小坂善太郎の前妻の直子の祖父は男爵・海軍軍医少将の高木兼寛、次男の兼二の娘。後妻の益子は、浄土真宗本願寺派の僧侶・政治家の大谷尊由の二女の益子。益子は朝香宮鳩彦王と允子内親王(明治天皇の第八皇女)の第2皇子・音羽正彦(7-1-1)侯爵と結婚したが子に恵まれず死別したため、善太郎の後妻として再婚した。前妻との間に1男の小坂順之介、後妻との間に1男1女を儲け、次男は政治家を継承した小坂憲次、長女の真理子は日生同和損保会長を務めた岡﨑真雄に嫁いだ。憲次の妻はまり子。
小坂憲次まで代々政治家家系を継承してきた。しかし、2015.11.25(H27)小坂憲次が悪性リンパ腫の治療専念のため第24回参議院議員総選挙に立候補をせず、小坂家から後継候補を擁立しなかったため、帝国議会以来続いた小坂家の国会議員として議席は一先ず終焉を迎えることとなった。
第277回 信州 小坂財閥 前編 4代続いた一族の議席
小坂善之助 小坂順造 お墓ツアー
|