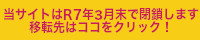兵庫県明石出身。1890(M23)東京帝国大学工科大学造家学科卒業後、日本橋に建築事務所を開く。先進的な技術に関心をもち、特に濃尾地震を契機として鉄骨構造の輸入・普及に努力した。日本の鉄骨建築の先駆者としての手腕は高く評価され、三井財閥の目にとまりスカウトされる。1892三井組に嘱託として入社。主に三井財閥の企業の建築物の設計を行った。1903旧三井本館を設計ではじめて鉄骨を用いるため、鉄骨構造調査で渡米し、カーネギー社から鋼材買付契約を行った。'03独立し横河工務所(現・横河建築設計事務所)を開設。また、母校の東京帝国大学建築学科で鉄骨構造の講義を持った。'15(T4)工学博士。
明治末年から大正初めにかけて鉄骨造の先駆的作品をいくつか残している。代表的なものに、日本初の近代劇場である帝国劇場の設計がある。これは日本の劇場建築では初めて観客席がすべて椅子席になり、オーケストラボックスを作り、天窓をとらず人工照明を使用するなど、革新的であった。この革新的なアイデアやブレーンとして活躍したのが、山陽鉄道で革新的なアイデアで激賞されていた西野恵之助(2-1-13)を帝国劇場株式会社の専務取締役に招いて実現したことである。帝国劇場は、渋沢栄一、西園寺公望(8-1-1-16)らが、日露戦争に勝利した国が外国の賓客を案内するに足る劇場をと提唱して尽力したものである。
また、煉瓦建築の地震に対する危険性を指摘して、独立で「鉄骨煉瓦造り」という耐震性をもつ工法を開拓した。その他、国会議事堂建設の際の委員も務めた。
横河工務所を創設後、横河橋梁製作所・横河化学研究所・横河電機研究所・東亜鉄工所・横河電機製作所・満州横河橋梁会社を創立し、実業家としての手腕をふるい横河グループを作り上げた。多忙な事業の右腕として、設計を主に長男の横河時介(同墓)、中村伝治、松井貴太郎らが助けた。また、一般的に普及していなかった『電気』に注目し、近い将来に電気が各家庭に行き渡る時代が到来することを予見して、甥の横河一郎(9-1-4-3)・青木晋に電気計器製造事業を託した。今まで外国製電気計器が独占する状況であったが、'17完成により国産化の道を開いた。
その他、民輔には色々な逸話が残っている。呉服店を主としていた三井家にデパートメントの経営形態を進言。科学的管理法の発案者であるフレデリック・テイラーの「テーラーシステム」を日本にいち早く紹介。琴が長すぎて運びずらいことより、折りたたみ式の琴を開発するための会社である倭楽研究所の創立などである。
'11建設業協会理事長(後に会長)に就任。'25(T14)〜'27(S2)社団法人日本建築学会会長。'43工務所を時介に譲り引退。中国古陶磁に対する眼識については専門家の高い評価を得るほどであり、中国古陶磁・古陶器の収集家でもあった。'32(S7)1200点の古陶磁を東京帝室博物館に寄贈し、ヨコガワ・コレクションとして収蔵されている。享年80歳。'64第1回日本建築祭で日本建築界先覚者遺徳顕彰5氏のうちの1人に選ばれた。
<コンサイス日本人名事典>
<人物20世紀>
<「HISTORY 横河のあゆみ」YOKOGAWA>
<人事興信録など>

*墓所内は正面に「工学博士 横河民輔之墓 室下枝」、裏面「1864-1945」の墓石が建つ。右側に横河民輔の銅像、銅像の背中に「工学博士横河民輔先生壽像 為 創立二十周年記念建之 昭和十一年十一月 株式会社横河電機製作所」とある。台座前面に「横河民輔先生」、台座裏面に略歴が刻む。左側に洋型「横河家」、右面「昭和四十九年十一月吉日建之」、裏面に横河時介の刻みがある。横河正三の刻みはない。また墓所入口に和型「横河敦子之墓 / 横河悦子之墓」が建つ。悦子は横河民輔の二女で2才で逝去。敦子は横河民輔の四女で2才で逝去。
*妻の下枝(しずえ)は漢学者の棚橋松邨と女子教育家の棚橋絢子の次女。下枝は陶磁器収集家としても著名。1893(M26)横河民輔と下枝は結婚。二人の間に3男4女(二女子は早世)に恵まれ、長男の時介は父の遺業を継承。三男の横河正三(1914-2005)も続き、横河電機代表取締役社長を務めた。
*右隣りの墓所は横河電機初代社長となった甥の横河一郎の墓である。横河民輔の兄の横河震八郎の長男。
第284回 横河グループ創始者 YOKOGAWA 日本の鉄骨建築の先駆者
横河民輔 横河時介 お墓ツアー
|