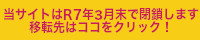台湾台北市出身。祖父は金井信生堂の創業者の金井直造(同墓)。父は2代目社長の出版人の金井英一、尚子(共に同墓)の二男として、当時父が勤めていた三井物産の赴任先で生まれる。のちに兄(長男)の謹一郎(同墓)は18歳の若さで亡くなったため跡継ぎになる。父が退職をし金井信生堂を継ぐため一家で内地に戻り、1936(S11)東京府武蔵野町市立盈進学園小学校入学。
'49 東京大学教養学部入学するも理学部に転部し、'54 同大学理学部生物学科卒業。大学院に進み「愛鷹山の植物」の地理的分布の研究を始める。植物分類学者の原寛(10-1-1)に師事し、ヒマラヤのマメ科コレクションの整理を行う。同じ分類研究室の先輩に山崎敬がいた。
'58.3 東京大学大学院生物系研究科博士課程中退し、同.4 東京大学理学部助手となり、'62 理学博士。'68.4 東京大学総合研究資料館助教授に就任。
当時の植物分類学は大きな変革期を迎えていたとされる。例えば、種の変異性の掌握では従来から重きを置いてきた外部形態の変異性に加え、地理学・生態学上の特性、さらには染色対数や核型解析による集団間の遺伝的変異性の存在などが考察できるようになり、これを受けて分類学においても従来とは異なる多様な研究法が生まれ、議論の活性化がもたらされた。しかし、金井は新たな登場した解析法を採り入れた分類群の研究には関心を示さなかった。
ヒマラヤ植物調査の専門家として、'60-'83の間に実施された東京大学ヒマラヤ植物調査隊の7回にわたる研究調査に参加し、'69.2-'71.3 第4次ではネパール派遣コロンポプラン専門家として現地参加した。ネパールから帰国後は総合研究資料館の最初の助教授となり、インド植物調査を引き継ぐことになった。この調査に先立って、東京大学から国立科学博物館に移った。
'72 第5次では隊長としてインド植物調査を組織した。この調査隊は当初、ブータンを対象国としていたが、国王が急死したことなどの事情があって入国できず、第二の候補地としたネパール東部とインド・ベンガル州のダージリンで現地調査を実施した。同.12 国立科学博物館植物研究部植物第一研究室主任研究官に就任し、翌年から室長となる(1973-1990)。'90.5(H2)国立科学博物館植物研究部長となり、'94.3 定年退職し、名誉館員。退職後は東京環境工科専門学校講師を務め、警視庁科学捜査研究所嘱託も務めた。
大人向けの観察会に嫌気がさし、子供だけを相手にする観察会を開くようになる。観察会では保護者を隔離し、植物の名前はなるべく教えないスタンスだった。また東京環境工科専門学校ではテキストを使わず、実物のみを使った植物分類学の講義をした。
植物分類学を始めた当初は日本植物の分布図を作る計画で大量のデータ処理にパンチカード方式を用いた。さらに電子計算機処理に移り、コンピュータを活用した。日本の植物学者で大量データ処理手法のパイオニア的存在として活躍した。日本植物学会では学術用語集植物学編の編集委員会の総括班幹事として電算処理責任者を務めた。
編著書は多く『日本地名索引』(全2巻:1981)、『新日本地名索引』(全3巻:1993)などある。『地名レッドデータブック』(新日本地名索引・別巻:1994)は、'95 日本家系図学会賞を受賞。'96『地名索引』三部作編纂の功績に対し「吉川英治文化賞」を受賞した。他に『日本植物分類学文献目録』(全2巻:1994)、『地図で見る 日本地名索引』『日本地名ファイル』(CD-ROM版:1998)、『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』(2008)などがある。急性心不全で逝去。享年91歳。