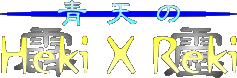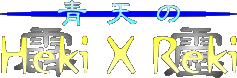|
- 1 -
「――陽光の火は蒼く騎士と刃を照らし、希望の凱風は尚吹き続く。
紅い炎と氷の雨は無を切り裂き、無に帰さんとす。
やがて虹が現れ、獣達と共に時を奏でる。
負が支配せし世は鐘の音によりて終焉し、民が望みし唯一の聖者は福音を齎す。
なんと悲しからずや、空は聖なれど聖なるは天に非ず――」
天気は良好、風は東。
教室の白いカーテンがやわらかに揺れている。
「・・・というのが心理学者の権威であるカイシン=キサラギが自身の著書に記した有名な一節だな。
聞いたことある奴もいるかもしれないが、この言葉の真意は・・・」
午後の最後の授業、暖かい陽射し、心地良いそよ風。
眠気に支配されるには、そう時間は要しなかった。
間もなくして、教室の隅の方で規則正しい整った寝息が静かに立ち始めた。
「・・・また寝てる」
黒いショートヘアーの少女の視線がこうべを垂れて眠っている少年に注がれている。
少女は「やれやれ」と言わんばかりに軽く肩をすくめ、視線を黒板に戻した。
少年はその後も授業が終わるまで完睡した。
「ふぁー・・・あ・・・んんー・・・」
校門を抜けてすぐに少年が両手を真上に伸ばし、全身でこれでもかと言わんばかりに欠伸をしている。
「呆れた。まだ眠いの?あれだけ気持ち良さそうに寝てたのに」
少年の横で少女が黒髪を掻き分けながら尋ねる。
二人は歩きながら話を続ける。
「んー、別に眠いっていうわけじゃないけど」
いたずらっぽく笑みを浮かべながら少年は答えた。
少年は、授業の時の整った服装とは違い、着崩した制服が似合っている。
「じゃあどうして欠伸してるのよ」
少女は少年より少し身長が低く、微妙に上目遣いをしながら少年に詰問した。
「儀式みたいなものかな。欠伸を思いっきりして今日一日を締めくくるっていうか。逆にしなかったら一日が終わった気がしないかも」
少年は大袈裟に真剣な表情をして答えて見せた。
「儀式・・・って」
少女ははぁ、と大きなため息をついた。
「陽亮ってさ、毎日何時に寝てるの?」
「えー?蒼碧ほど遅くはないと思うけどな。十時」
蒼碧と呼ばれた少女が問い、陽亮と呼ばれた少年が答えた。
「じゅ・・・十時!?それで朝は何時に起きてるの?」
「えと・・・七時半だっけ」
「・・・九時間半も寝てるの?なのに授業中も眠いっておかしいわよ」
「仕方ないだろ。眠いものは眠いんだから」
「・・・」
蒼碧は呆れ果てて返す言葉が見つからなかった。
対する陽亮はあっけらかんとしていた。
「あ、やっば。教室に世界史の教科書忘れてきた」
陽亮はそう言うと、校門の方を振り返った。
「教室まで取りに戻るから先に帰ってていいぜ?」
陽亮は蒼碧に手を振りながら校門に向かって走り始めた。
蒼碧は咄嗟に身を翻し、陽亮に向かって、
「え?あ、あたしここで待ってるからっ!」
と叫んだ。
「おーう、サンキュー」
陽亮も蒼碧の方を振り向き、こう叫んだ。
そして陽亮は校門の方へ走っていった。
「待つに決まってるじゃない・・・」
蒼碧は誰にも聞こえないようなか細い声で呟いた。
「それにしても・・・帰っても勉強とかしないくせにこういうところはマメよね」
陽亮の遠ざかる後ろ姿を見つめながら蒼碧は再び呟いた。
陽亮が校門の中へ消えていくのを見送り、蒼碧は塀に背中を付けて寄りかかった。
それにより、上体が上を向き、自然と蒼碧の視界の中に春の空が広がった。
雲ひとつない真っ青な快晴の空だ。
「んー。いーい天気だねー」
蒼碧は日向ぼっこをする猫のように目をとろん、とさせて空を満喫した。
蒼碧の額に暖かい陽射しがふわっと舞い降り、頬を微風がそっと撫でた。
蒼碧は陽亮に倣い、両手を上に伸ばし、背伸びをした。
そして深呼吸を一つ、二つ。
いつもと変わらない、平穏な四月の空だった。
続けて蒼碧が三つ目の深呼吸をしようとしていた時にそれは起こった。
ズドォォォン!!
これまでに体験したことのない轟音と衝撃波が蒼碧を襲った。
「きゃあっ!?」
蒼碧は何が起こったのか理解することができなかった。
それと同時に蒼碧は衝撃波でビリビリと振動する塀から弾かれた。
塀に身を委ねていた蒼碧はバランスを失い、道に投げ出されてしまった。
蒼碧は反射的に両手で耳を塞ぎ、目を閉じてその場に蹲った。
蒼碧にとっては不意のことでパニックに陥りそうになった。
それから暫く蒼碧はそのままの格好で震えていたのだが、轟音と衝撃波はそれ以来音沙汰がなく、一度きりで収まっていたようだった。
「・・・?」
恐る恐る蒼碧は耳を塞いでいた両手を離し、片方の瞼だけ少し開き、辺りを確認した。
蒼碧は自分を投げ出した塀の向こうのグラウンドが騒がしくなっていることに気がついた。
「何が起こったんだろう・・・?」
蒼碧は立ち上がり、校門の方へ走って行った。
「おーう、サンキュー」
蒼碧にそう言い残し、陽亮は校門へ向かい、走った。
校門を抜けると真正面に校舎の玄関がある。
そこへ行くためにはグラウンドを横断しなければならない。
陽亮は下校してる生徒の波とは逆の方向へと走って行った。
「俺ってそんなに睡眠時間長いのか?」
蒼碧から言われたことを気にしつつ、陽亮は校舎の玄関に小走りで向かって行った。
陽亮と蒼碧の二人は、傍目から見るとまるで恋人同士のようだった。
しかし、二人にはそのような関係はなく、幼馴染みというだけのことであった。
毎日一緒に下校すれば、周りの人間に「この二人は恋人同士」という認識が芽生えるのは避けようがなかった。
陽亮は、ふっ、ふっ、と軽やかな息遣いでグラウンドの中央付近まで到達した。
そのとき、陽亮の辺りが不意に明るくなった。
それは目も開けていられないほどの明るさだった。
雲が消えて晴れ間が見えた、ということではない。
元々今日は快晴のはずだ。
そして次の瞬間。
ズドォォォン!!
陽亮は明るくなったと感じる間もなく、正体の分からぬ衝撃に襲われた。
「ぐあぁっ!!」
陽亮は計り知れない激痛に咆哮した。
自分の身に何が降りかかっているのかも把握する暇もなく、陽亮は意識を失い、膝から崩れるようにして地面に落ちた。
- 2 -
「・・・け・・・すけ・・・して・・・ようすけ・・・陽亮っ!」
陽亮は自分の名前を呼ばれる声で意識を取り戻した。
「陽亮っ!大丈夫!?痛いところない!?」
「・・・ん・・・ぅ・・・あ、あお・・・い・・・?」
陽亮はゆっくりと目を開いた。
途端に太陽の光が陽亮の瞳を直撃し、今度はゆっくりと眩しさを感じられた。
「おー、気がついたぞ!」「良かったぁ、生命に別状はないみたいね」「でも、びっくりしたぜ」
陽亮の周りを取り囲んでいたギャラリーから安堵の声が上がった。
放課後であるこの時間帯のグラウンドには、クラブ活動をする生徒や下校する生徒で溢れていた。
そこへ得体の知れぬ衝撃、そして倒れている制服姿の男子生徒。
数え切れないほどの野次馬が陽亮の周りを取り囲むには一分とかからなかった。
「陽亮っ!大丈夫・・・?立てる?」
「あぁ、多分・・・。よっ、と」
陽亮は立ち上がり、服についた砂埃を手で払いのけた。
「・・・何ともないの?どこか痛かったりしない?」
蒼碧が泣き顔で心配そうに尋ねるが陽亮は
「大丈夫、大丈夫」
と言って手をひらひらと振って見せた。
ギャラリーは、
「今のって雷だよな?」
「多分・・・」
「でも雲なんて何処にもないぜ?」
「っていうかさ、雷に打たれて無事だった人っているの?」
「んなこと俺に聞かれてもな・・・」
「じゃあ今の光は何だったんだよ、結局」
という議論で盛り上がっていた。
ギャラリーが盛り上がっている隙に、陽亮はそそくさとギャラリーの輪の中から脱出した。
「あれ?あいつどこ行った?」
陽亮は危うく時の人になりかけるところだった。
陽亮は一緒に脱出した蒼碧に何かを言い残した後、校舎の中へと消えていった。
「・・・本当に大丈夫なの?」
「大丈夫だってば。何処も痛くないし」
「心配だなぁ・・・」
「おいおい、泣くなって。心配要らないさ」
「だってすごくびっくりしたんだよ・・・?」
「悪い悪い、大丈夫だって。もう泣くなよ、な?」
「・・・うん」
「おっといけね、教科書取って来なきゃいけなかった。・・・じゃ、取ってくるよ」
「・・・うん。気をつけてね?」
「気をつけるって、何をだよ。あはは!」
「・・・むー、じゃああたしここで待ってるからね」
「あいさっ!」
このやり取りの後、陽亮は校舎へ入っていった。
「今の・・・何だったんだろう?陽亮、本当に大丈夫かな・・・」
蒼碧が真っ赤に泣き腫らした目で空を見上げて呟いた。
蒼碧の視界には雲一つない春の空が広がっていた。
この後蒼碧は、教科書を取って戻ってきた陽亮と一緒に下校した。
蒼碧はそれぞれの家に通じる分かれ道のところでもう一度「大丈夫?」と尋ねたが陽亮は「大丈夫」と返答した。
そして手を振る別れの儀式の後、蒼碧は西に、陽亮は東に歩き始めた。
- 3 -
いつものように始業十五分前に教室に入った蒼碧は、いつもとは違う光景を目の当たりにして驚いた。
普段は遅刻ギリギリで教室に滑り込むことが日課である陽亮が、窓際の席にぽつんと座っていたからだ。
昨日のことを心配していた蒼碧だったが、それよりも目の前の有り得ない状況による驚きの方が強かった。
「あれ!?珍しいこともあるものねぇ。どういう風の吹き回し?」
教室の中の人影はまだ疎ら。
蒼碧の澄みきった声が教室に響く。
「朝、人に会ったら『おはよう』と言いなさいって、親から教えてもらってないのか?」
陽亮は片方の眉を少し上げて蒼碧を横目で見ながら愚痴った。
「はいはい。オハヨウゴザイマス」
蒼碧は異国人のような口振りで陽亮に挨拶した。
陽亮は「よろしい」と言って満足気に頷いた。
「・・・それで、何でこんなに早いの?」
「いや、別に。・・・何だよ、俺がこんなに早く来ちゃ悪いのか?」
「そんなこと言ってないわよ。明日からもずっと続けて欲しいものね」
「あー無理」
「諦めるのが早いわねぇ」
「潔い、って言ってくんないかな」
陽亮と蒼碧がこうしたやり取りをやってるうちに続々と生徒が教室を埋め、始業のチャイムが鳴った。
若い女の担任教師が教壇で出席を取り始める。
「はーい、席に着けー。出席取るわよー」
さっきまで乱雑だった生徒たちのポジションが、徐々に規則正しく整列されはじめた。
話に夢中で席に着こうとしない男子の集団がいたが、
「ほらほら、そこの男共。朝っぱらから下ネタで盛り上がってないで早く席につかんかい」
と女教師が一掃した。
濡れ衣を着せられた男子生徒達が反論したが、他の生徒達の笑い声のせいでそれが女教師の耳に届くことはなかった。
「じゃあ、まぁ、そんなこんなで出席取るぞー。赤星ー」「うす」「安達ー」「うぃー」「伊原ー」「はーいっ」
いつもと変わらない一日が始まった。
(あの様子じゃ大丈夫だったのかな・・・よかった)
蒼碧は一瞬だけ不安な表情を浮かべ、次は陽亮の姿を見て微笑んだ。
「紺青ー。・・・あら?いないの?こんじょーう!」
「・・・あっ!はいっ!」
蒼碧は陽亮のせいで危うく欠席になるところだった。
- 4 -
「変。」
「な、何だよ、急に」
普段通り二人一緒に、普段通り帰る道で蒼碧が陽亮に投げ掛けた台詞は「変」の一言だった。
「だって、変だったんだもん。今日の陽亮」
蒼碧がこう言うのには理由がある。
授業中に寝ない日がない陽亮が今日は一度も寝なかったからだ。
少なくとも、蒼碧が監視したタイミングでは陽亮の寝た姿を目撃できなかった。
蒼碧が今朝感じた安心感はとっくに吹っ飛び、昨日感じた不安感を再びつのらせていた。
「何処がどういう風に変だと感じたんだよ」
「授業中に一度も寝てないからよ」
陽亮が訝しげに訊き、蒼碧が訝しげに答えた。
「そうだっけ?そういえば今日は寝てない気がするな」
「それにさ、寝てない時に何してるのかな、って思って見てたんだけど」
「ああ」
「教科書見るでもなく、ノート取るでもなく、ただぼーっとしてた様に見えた」
「そ、そうか?」
陽亮の表情に焦りの色が現れ始めた。
「ねぇ、何処か身体の具合おかしいの?・・・やっぱり、昨日の雷みたいなものに打たれたから?」
「い、いや、べ、別にそんなんじゃ・・・ないけど・・・」
陽亮の呂律が回らなくなってきた。
「本当に大丈夫だったの?あの後」
「だ、大丈夫だって言ってるだろ?何処も痛くも苦しくもないし!」
陽亮は回っていない呂律を無理やり回し、早口で捲くし立てた。
陽亮の表情の焦りの色は最早顕著なものだった。
(やっぱり・・・何か隠してるわね・・・)
蒼碧は確信した。
「ふーん・・・ところで陽亮、昨日何時に寝たの?」
蒼碧は所謂『女の勘』で、陽亮に昨夜就寝した時刻を訊いた。
「え!?・・・あ、うーん、えーっと・・・確か十時・・・だったかな?」
陽亮はぎくり、として冷静な受け答えが出来なかった。
「なんで回答に詰まるのよ。本当は何時なのよ!?」
蒼碧は陽亮の回答を信じず、更に詰問した。
陽亮は、蒼碧の迫力に気圧され、
「もしかしたら、十一時・・・だったかもな・・・」
と口籠もりながら呟いた。
蒼碧は容赦なく攻め続けた。
「本当のこと言ってよ!」
陽亮は最早目の焦点が定まらなくなっていた。
「少なくとも・・・十二時には・・・寝てたんじゃないかな・・・」
蛇に睨まれた蛙の様に小さくなっていく陽亮に向かい、蒼碧は止めを刺す。
「嘘。三時くらいに陽亮の部屋の電気点いてたもん」
「な、何で知ってんだよ!?」
険しかった蒼碧の表情は一気に呆れ顔へと変化した。
「はぁ・・・あのねぇ、あたしがそんなこと知るわけないじゃない」
「なっ・・・あー、やられた・・・」
古典的な誘導尋問にまんまと陥れられたことに、陽亮が気付いた。
「まさか徹夜ってことないわよね?」
「・・・」
「徹夜なのね・・・」
陽亮は嘘が表情に出る悲しい性を持っていた。
陽亮はとうとう観念し、これ以上隠し事は出来ないと悟ったらしく、自ら重い口を開いた。
「実はな、昨日あれから家に帰って、シャワー浴びてメシ食って寝る時になってもずっと身体が火照ったまんまでさ」
蒼碧は、
「(陽亮って、シャワーの後にご飯食べるんだ・・・)」
と、ふと思ったが、話題の方に興味があったため、相槌を打つだけで我慢した。
陽亮が続ける。
「あの衝撃を受けてからしばらくは頭が冴えててさ。世界がスローモーションみたいに見えるんだよ」
「世界がスローモーションみたいに見える?」
蒼碧が陽亮の言葉をボイスレコーダーのように再現し、聞き返した。
陽亮がそれに答える。
「ああ。・・・なんだろうな、こう・・・全ての感覚が鋭くなってるっていうか・・・そんな感じだった」
「すばしっこい虫も手掴みで取れそうなくらい、自分以外の世界がゆっくり動いてた・・・気がした」
「今はもう普通の状態に戻ってるんだけどな」
陽亮は視線を空に向け、更に続ける。
「・・・普通はさ、ベッドに横になって電気消したらすぐに眠って気付けば朝、っていうパターンなんだけど」
「昨日は全然眠れなくて・・・いくら目を閉じたままでも一向に眠くならなくて」
「あ、言っとくけどな、十時過ぎにはもうベッドに入って寝ようとしてたんだぜ?」
蒼碧は
「分かったわよ・・・それで続きは?」
と急かした。
陽亮が話を再開する。
「ああ。それから二時間くらい必死に寝ようと頑張ったけど眠れる気配さえしなくてさ」
「しょうがないから十二時くらいにベッドから出て、明かりつけて」
「朝までずっと雑誌読んだり音楽聴いたりしてた」
話が終わると陽亮はそれまで遠い目をしていた視線を蒼碧へと戻した。
蒼碧は納得してるやら呆れてるやら分からない複雑な表情をした。
「そう・・・それで、一睡も出来ずに学校に来たわけね」
「ああ」
陽亮は申し訳なさそうに返事をした。
「そんなことだろうと思った。陽亮があんな時間に学校に来てるなんて絶対何かあると思ったもん」
蒼碧は口を若干尖らせながらそう言った。
「そんなに俺に学校へ早く来て欲しくないのかよ」
陽亮は不満そうな顔で愚痴った。
「今日は帰って早めに寝なよ。身体、壊すよ?」
蒼碧は心底正直な想いを吐露した。
「え、あ、おう」
蒼碧に愚痴を見事なまでにスルーされて不意を突かれたため、陽亮は空返事になってしまった。
それから電信柱二本分程、二人とも無言の時間が続いた。
西日を浴びた二人の影が左に伸びている。
ほんの少し前を歩いていた影が突然歩みを止め、ほんの少し後ろを歩いていた影がそれを追い越した。
ほんの少し後ろを歩いていた影――今となっては前にいる影――がそれに気付き、同じく立ち止まって追い越された影の方を振り返る。
先に口を開いたのは追い越された方の影の主だった。
「・・・悪いな、隠そうとして」
追い越した方の影の主、蒼碧がきょとんとした顔を作る。
「え?」
追い越された方の影の主、陽亮は神妙な面持ちをしていた。
「・・・蒼碧に心配とか掛けたくなかったから・・・さ」
「あ、うん・・・」
陽亮から予想していなかったことを言われ、蒼碧は戸惑った。
「えっと・・・」
蒼碧が口籠っていると、陽亮が再び歩み出し、何も言わずに蒼碧を追い越した。
「・・・あ、待ってよ!」
蒼碧は慌てて振り返り、二、三歩だけ走って、陽亮に追い付き、走ることをやめて歩き出した。
「・・・ありがとう」
何も礼を言われるようなことはされていないはずだが、蒼碧は思わず感謝の言葉を口にした。
蒼碧は嬉しいのか恥ずかしいのか良く分からない感情を抱き、顔が紅潮した。
陽亮にその表情を見せたくなかったからか、蒼碧は俯いた。
それからまた暫く二つの影は無言で歩いた。
「・・・じゃあ、また明日な」
蒼碧は陽亮にそう言われるとふと我に返り、俯いていた顔を俄かに上げ、辺りを見渡した。
蒼碧が気付かぬうちに二人はそれぞれの家に通じる分かれ道に達していた。
「あ、うん、また明日ね」
蒼碧は出来るだけ冷静に振舞った。
「おーう」
陽亮が答えた。
「ちゃんと寝なきゃダメだよ?」
蒼碧は念を押した。
「分かってるって」
陽亮はぶっきらぼうに答えたが、表情は微笑んでいた。
そして手を振る別れの儀式の後、蒼碧は西に、陽亮は東に歩き始めた。
- - - Go to NEXT PART.
|