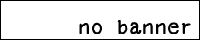記念日
女は、とかく何かと記念日を設けるのが好きだと、ギロロは内心でため息をつい
た。何でその程度の事でと思ってしまうような理由もあり、そして忘れた日には
、とてつもなく不機嫌になってしまう。
正直、男であるギロロにとって、それは面倒事以外の何物でも無い。勿論、そん
な様子は?にも出さないが。
何しろ、こんな事を考えているなどと悟られては、今目の前でうきうきと何やら
準備に奔走している少女が、怒り出す事は明白なのだから。結局、面倒だ何だと
考えながらもこうしてその姿を見守っている時点で、自分は彼女に甘過ぎるのだ
ろうと思う。
自宅庭の芝生は青い。その中に日の光を眩しく反射する白いテーブルクロスを広
げていた少女が、ツインテールの赤い髪を揺らしてギロロを振りむいた。思わず
ドキリと動きを止め、しかしすぐに何食わぬ顔を装い、こちらへ歩いて来る少女
を迎える。表面上は普段と変わらない、眉間にしわを寄せた一見不機嫌そうな面
構えだ。
「どうした」
「もう、ちょっとはギロロも手伝ってよ!」
腰に手を当て、ギロロを、まるで小さな子どもを叱るように振る舞う。元から家
事全般が得意なのは知っているが、この年からこうも母親然としていて、それは
一般的には称賛に値するのだろうが、果たして本人の為なのかどうかギロロに分
からない。
最近、頓にキャリアウーマンである母親に似て来たようだ。テキパキと家事も仕
事もそつなくこなす。もっとも、彼女にとっての仕事は、まだ学業な訳だが。
「聞いてるの?」
自分に対するこの扱いにもだいぶ慣れたとは言え、心中ではやれやれと重い息を
吐いた。何にせよ、子供のやる事だと思えば腹もそんなには立たない。その子供
に見下ろされる自分の体格に、少々自虐的に傷つくくらいで。
「しかし、何をしたら良いんだ?」
庭に広げられたテーブルや椅子などのパーティー用具一式。料理は彼女が母親と
共に作り終わっている。後は並べるだけだが、それは来賓を待ってからになるだ
ろう。もっとも、客と言っても何時もの騒がしい愉快なメンバーな訳だが。
「何かよ何か!自分で探しなさいよね、ホントにもう」
何故怒られているのかさっぱり分からないが、とりあえず素直に謝ると、少女は
夏の太陽のように満面の笑み振り返る。
「何しろ、今日は私とギロロが出会って、丁度10年の記念日なんだから!」
晴れやかに笑い、少女が駆けて行く。その後姿をぼうと眺めていたら、ふっと頭
上から影が落ちた。そっくり返るように上を見ると、夏美がニヤリと年頃の女性
に相応しくない、少年のような笑みを返して来る。
本当に、困った事に、少女と夏美は瓜二つだ。
「何故、あんな回りくどい言い方をするんだ」
ただ、自分の10歳の誕生日だと言えば良いだろうに。すると夏美は、妻は、今
度は母親の顔で笑う。
「背伸びしたいんでしょ。女の子だもん」
「そういう物か?」
良く分からないが、夏美には分かるのだ。それが同性故なのか母親だからなのか
、ギロロには判断がつきかねる。
近頃は娘にまで朴念仁と呼ばれてしまう。おかげで、自分は鈍いらしいという自
覚だけは明確になってしまった。
「ああそうだ、どうせ連中が来たら忙しくなるだろうから、今の内に渡しておく
」
まるで思いついたようにさり気無く、何気ない風を装って、ギロロは随分前から
買っておいたそれを、ぽんと妻に向かって放り投げた。そのままでは顔面にぶつ
かる小さなリボン付きの箱を、夏美は無駄の無い動きで軽やかに受け止める。
成人しようが母親になろうが、ギロロの見抜いた彼女の戦士として力量に衰えは
無い。むしろ増している感さえある。
「これ…」
「あいつの10歳の誕生日だと言う事は、お前が母親になって10年目の記念日
だって事だろう?俺からの…その…、何だ。感謝の、気持ちだ」
記念日何て、面倒な事この上ない。だがギロロは、どれ一つとして疎かにした事
は無かった。この10年、一度も。
母親は毎日が戦争だ。傍で見ていてもそう思う。だから10年間よく頑張ったと
、そしてこの先の10年も、20年も、30年も、ずっとずっと『これからも宜
しく』と、祈りにも似た願いを込めて。
あまりリアルな数字は、なるべく考えない。ギロロの願う『ずっと』と彼女の言
う『ずっと』の間に、実質的な時の長さが壁となって聳えているから。
今日は記念日だ。だからなるべく、笑っていよう。笑って居て欲しい。そんな日
が、何時もだったら良いと思う。
嘘だ。本当は面倒じゃない。本当は嫌いでも無い。彼女と、彼女等と祝う記念日
は、本当は好きだ。
「…ありがとう…」
ふいをつかれたらしい夏美のぽかんとした顔は、ひいき目を指しい引いてもまだ
まだ幼い。時折、娘と並んでいると姉妹のよう錯覚する事さえあるくらいだ。そ
れがギロロの秘かな自慢であると、勿論、当人は知らない。
「どうしよう、私は何も用意してない」
箱の中には、控え目なデザインの赤い石をあしらったネックレス。瞳を輝かせて
魅入っていた夏美が、慌てたようにギロロを振り返った。
「俺?俺は別に、何も無いだろう?」
きょとんとしていると、まだ出会ったばかりの頃のように、強気な瞳で人差し指
を付きつけられる。
「何バカな事言ってんのよ。私が母親10年目なら、あんたは父親10年目って
事でしょう?」
まだあの掌が自分よりもずっと小さかった時、握り返して来た指の強さを今でも
よく覚えている。ただでさえ、父親と子供の繋がりは、母親のように目に見えて
分かり易くは無い。その上、結局自分と娘の見た目は全く違う。己で選んだ事と
は言え、正直、父親になれる自信なんて無かった。
それが、今はどうだ。
「そうか、俺ももう、父親をやって10年になるのか…」
すっかり、この立ち位置に慣れてしまっている。何かそれまでに色々な苦労をし
た気がするのだが、思い出すのは楽しい記憶ばかりだ。
「しかしなぁ」
思わず、今度こそ隠しきれずに妻に向かってぼやく。
「ちょっと前まではお父さんだったのが、何で急に名前で呼ぶようになったんだ
?」
何だか少しだけ寂しい。反抗期だろうか。
すると夏美は気落ちする夫と視線を合わせるようにしゃがみ込み、額の黄色いド
クロを人差し指でつついた。
「それは、私とライバルだからって事でしょ」
「はぁ?」
「ギロロのお嫁さんになりたいんだって」
「えっ」
絶句するギロロに夏美は、負けるつもりも無いけどねと笑う。板挟みのギロロは
、もう冷や汗しか出て来ない。どっちに良い返事をしても、後に待っているのは
似たような怒り顔なのだから。
「そう言えば、あの子への誕生日プレゼントは?」
「ああ、ちゃんとねだられた物を買って来たぞ」
「ホント、子供には甘いわね」
肩をすくめると、夏美は噴き出した。その言い草に、少しだけカチンと来る。別
に彼女に、他意はないのだろうが。
「言っとくがな、夏美。俺が昔からお前に甘かったのは、お前が子供だったから
じゃないからな」
仕返しは見事に成功し、夏美はパーティーが始まってからもまだ、上気した頬で
照れていた。
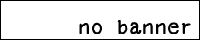
はまぐり。/クロ 様