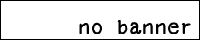「ギロロ、お昼できたよ」
エプロン姿のまま、夏美はひょいとリビングから庭へと顔を出した。
赤いテント、ぱちぱちと音を立てるたき火。傍のブロック。
ギロロだけが掻き消えていた。
一瞬前まで、そこにいた筈だ。
始末されていないたき火がそれを知らせる。
冬樹あたりなら、マリーセレスト事件を思い出すだろう。それはさておき。説明できない胸騒ぎが夏美を襲う。
理屈でなく感覚で、夏美は何かが起こったと思ったのだ。
カコッ
サンダルを引っ掛けて、夏美は庭へと下りた。黄色のエプロンがひらりと翻る。(ひるがえる)
周囲を見回すが、ギロロがいなくなった原因が分かる筈もない。
既にキッチンのテーブルについていたケロロが、小首を傾げた。同じく席についていた冬樹に目で合図を送り、そこにいることを指示する。
ケロロも何かを感じたのだろう。
タタッと夏美同様に庭へと下りた。
「ギロロ〜。夏美殿のご飯でありますよ」
どこか茶化した台詞でケロロはギロロのテントをめくった。
思ったとおり、そこには誰もいない。ケロロは分かりづらく眉をひそめる。
「ボケガエル、どういうこと?」
「どーと言われましても。我輩にも何がなにやら」
"今度は何をしでかした"と言わんばかりの夏美にとんでもないとケロロは全身で疑いを拒絶した。本当に知らないらしい。
ケロロの態度にはわたわたしつつも後ろめたさは感じられなかった。ある意味でケロロはとても分かり易いところがある。
さすがに冬樹もリビングから庭へと顔を出した。
ギロロが夏美との一時を楽しみにしていることは態度で分かる。ギロロもケロロとは別な意味で分かり易いタイプなのだ。
大体、律儀な彼が昼食を共にする約束をたがえてしまうのは考えにくい。何かあったと思うのが−−論理的だろう。
冬樹はそこまで考えて、放置されていたたき火を見下ろした。
パカン!
日向家の庭、その一部がギミックのようにせり上がった。簡易式エレベータの中にいるのは黄色の曹長・クルルであった。
「クーックックッ、ぐえっ」
劇的登場も、その直後。夏美に片手で頭をわしづかみにされると形無しというものである。
「やっぱり、あんたの仕業ね」
完全に座った瞳で、夏美はクルルをねめつける。
それにしても、夏美は片腕、しかも腕を伸ばした状態でクルルの頭をわしずかみにしているのである。恐るべきパワーだ。
ケロロ達の体重は5.555キロぐらい(?)。女子中学生が片手で掴むには決して軽くはない重さ、だ。
「それで、ギロロはどーしたでありますか?」
今回ばかりはクルルに同情することなく、ケロロは夏美の隣でクルルを見上げた。
ケロロは疑いの目をクルルへ向けている。
「ククッ。向こうの俺が先輩を引っ張ったんだぜぇ」
「この我が小隊の問題児がぁ!!夏美殿、やっちゃえであります」
「ボケガエルに言われるまでもないわ!」
ぎゅっと夏美はわしずかみにしている手に力を込める。
「ククーッ。締まってる!!締まってるって!!」
「ん?向こうの俺?」
冬樹は呆れたように、けれどクルルを庇う気にもなれず、ただ眺めていた。しかし、クルルの言葉に何かが引っかかる。そして、その意味に気付いた。
冬樹は夏美に声を上げた。
「待って、姉ちゃん。ここのクルルは何もしていないかもしれない」
「え?」
「冬樹殿、どういうことでありますか?」
夏美の手から力が抜け、ぼとっとクルルは落ちた。
クルルは頭の痛みに顔をしかめている。とはいえ、夏美を責める気にはなれなかった。
なぜなら、これは。クルルの不始末とも言える物だからだ。
「もしかしたら。でも、間違っているかもしれない。そんなことが可能とは−−」
「いんや、日向弟。合っているぜぇ。先輩は他の世界に引っ張られちまったんだよ。−−俺が理論構築していたシステムを他の世界の俺も作り上げちまったんだ」
一同は場所をクルルズ・ラボへ移した。
ケロロは己の玉座に座り、一同、ここではケロロ、夏美、冬樹を見回す。
「つまり、他の世界、パラレルワールドのことだよね、曹長?」
「そう、平行空間。SFじゃよくある設定だよな」
「そこんとこがよく分からないであります。こことは違うけど、そこもギロロが居るのでありますか?」
「まったく同じ先輩がいるわけじゃねぇ。大体、全く同じ世界なら複数存在する必然性がない。つまり、各々異なる世界である以上、異なる先輩が存在することになる」
「何だかわけが分からないわ。ギロロはギロロなんでしょ?」
「んー、例えばなんだがよぉ。隊長と幼馴染でない先輩の世界だとする。そうなると、先輩と隊長の間柄は違ってくるだろ?」
「関係性の違い?そういうことかな」
「繋がりの違い、かもしれねぇがそういうことだ」
「我輩、頭が混乱してくるでありますよ。結局、ギロロを引っ張って何がしたかったで−−」
「先輩を9人引っ張って、起動歩兵10人化計画だな」
ケロロの言葉を遮って、クルルは言った。それと同時にケロロへレポートの束を放り投げる。わたわたお手玉しながら、ケロロはそれをキャッチした。そのレポートの表紙には"ギロロ伍長、10人化計画"とある。
そのレポートを覗き込んでいた夏美と冬樹、そしてケロロはタイトルを読んだ後にクルルを見た。
クルルは居心地が悪そうに玉座へ座りなおした。皆の視線に不機嫌全開で言う。
「ああ、分かっている。他の世界の俺に先越されたんだよ」
急遽、作り上げられたシステム。それはこちらの人間を特定の世界へ送り込むものである。ちなみにギロロが引っ張られた世界の情報は、引っ張られた時の時空歪みから取得済みだ。
簡単に言うと、空間軸、時間軸などのデータである。
これにより、引っ張ったり送り込んだりが可能になるのだ。
システムの転送エリアに入ったのは夏美とケロロだ。ギロロの迎えにこの二人が行くことになったのだ。ケロロ一人では不安だと夏美が言い張ったからだが。実のところ、夏美がギロロを心配していることは明らかであった。
夏美とケロロは揃い(そろい)の腕輪をつけている。居場所を特定するものであり、二人はギロロの分も預かっていた。
冬樹は心配げに二人を見ている。夏美は安心させるように小さく手を振った。ケロロはあいまいな笑みを冬樹に返した。
システムの設定をしていたクルルが二人に振り向く。
「んじゃ、いくぜぇ」
「OKよ」
「ねー、クルル。これ、痛かったりしないでありますよね?」
歯科待合室に居る子供のようにケロロは不安そうにしている。反対に夏美は平然としていた。首元にはパワードスーツチョーカーがあり、無意識だろうか夏美はそっとチョーカーに触れた。
パワードスーツは向こうで何があるか分からないための保険である。
「痛かないが、眩しいと思うぜ。ぽちぃ、と」
サッと濃い目のサングラスを何時もの眼鏡の上にかけるクルル。
カカッ
莫大な光が部屋を飲み込んだ。
「きゃ!」
「わっ!」
「ケロ〜!?」
すうっと光が収まると−−ケロロと夏美の姿は消えていた。
実験の成否を聞くように冬樹はクルルの方を振り向く。ちょうどクルルは例のサングラスを外していたところであった。
ひらひらとクルルはサングラスを振ってみせる。
「ちゃんと向こうへ送ったぜぇ。先輩を連れて帰れるかはあの二人にかかっているがな」
「軍曹と姉ちゃんだから大丈夫だよ」
どこまで分かっているのやら、とクルルは冬樹を見つめた。
そして、にやりと笑う。
分かり易い態度のギロロだ。いくら鈍い冬樹でも気付いているのかもしれない。
"それこそ、どっちでもいいか"
クルルは彼らをこちらへ引っ張る合図を待つべく、再びシステムへとその身体を向けたのだった。