 3度目のチェコ・フィル。聴いた回数ではウィーン・フィルに並んだ。
3度目のチェコ・フィル。聴いた回数ではウィーン・フィルに並んだ。最初のノイマンのときに「モルダウ」から3曲を聴いたから、
前回のコバケンとあわせ、2.5回目のチェコ・フィルの「わが祖国」。
 3度目のチェコ・フィル。聴いた回数ではウィーン・フィルに並んだ。
3度目のチェコ・フィル。聴いた回数ではウィーン・フィルに並んだ。
最初のノイマンのときに「モルダウ」から3曲を聴いたから、
前回のコバケンとあわせ、2.5回目のチェコ・フィルの「わが祖国」。
開演直前、なんと2、3階席は半分も入っていない。
ほぼ全部埋まったのは我がPブロックくらいだ。
「チェコ・フィルのわが祖国」では札幌では客が集まらないか?
いっそ「のだめ・・・」のヴィエラ先生で売ったらよかったかもしれない。
「ヴィシェフラド」はハープの美しく豊な響きでスタート。
マカルは最初の入りだけを指示して、あとは自由に弾かせていた。
その後シンバルは一発目を打ち損じ、トランペットはメロメロ、
およそチェコ・フィルらしからぬ前半だったが、
終盤には美しい弦の響きを軸に堂々たるクライマックスを聴かせた。
続く「モルダウ」からは自信のある音楽が復活。
なといってもホルンが威勢がいいのが楽しい。
ちょっと野暮ったい農民の踊り、ティンパニの迫力たっぷりのヨハネの急流。
スケールの大きいヴィシェフラドと好演。
前半締めくくりは「シャルカ」、見事なクラリネットソロから始まるコーダの追い込みは圧巻だった。
後半はルール違反をして、上のグレードの席へ移動。
直接音が少なくなって迫力は弱まったが、弦の響きを中心にチェコ・フィルサウンドを楽しめた。
後半も1曲目「ボヘミアの・・・」でコントラバスの入りが遅れ響きが混沌とする事故があった。
後半3曲では全般にわたって渋く、揺るぎのない音楽だった「ターボル」が一番。
マカルの指揮は曲によっては譜面(ミニチュア・スコア!?)をめくり、
余裕のない雰囲気をしばしば見せるのがちょっとショボイが、
総体的に全体の流れはイン・テンポでオケに任せ、隈取はきっちりというのが成功していたと思う。
しかし、二つの目だった事故を含め、オケの響きの密度が薄くなるようなシーンを感じたのは、
旅の疲れか、辞任の影響か?時折求心力というか集中力が途切れるように思われた。
弦楽器はマカルのスタイルに沿って、メリハリはあるがそれほど濃厚な表情を
見せることはなかった。
前後半でメンバーが入れ替わった管楽器。
ホルンパートが終始好調を持続。ケイマル不在のトランペットは全くの不発。
オーボエ、クラリネットと木管のソロは随所で秀逸。
好きな曲、好きなオケだから細かいことも気になるが、
「ブラニーク」のコーダのファンファーレがかっこよく決まれば大満足。
6割程度の入りと寂しい聴衆も、盛大な拍手を送った
終演20:50
終演後ホワイエではマエストロがサイン会。
テーブルに用意されたミネラル・ウォーターではなく、
別のスタッフからの「アサヒ スーパー・ドライ」手にしていた。
サインをもらい、言うに事欠き「ありがとうございます!」
マエストロはニコリとして"You are welcome"と応えてくれた。
3月札幌へおいで〜、コ○ケンの代わりに(^^;
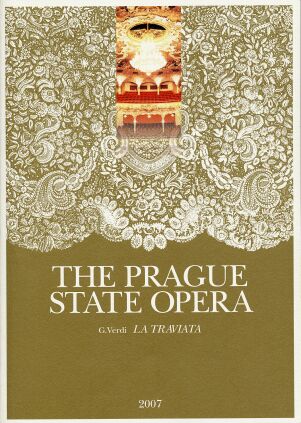 昨年11月のキエフ・オペラの「アイーダ」に次ぐ来日オペラ第2弾。
昨年11月のキエフ・オペラの「アイーダ」に次ぐ来日オペラ第2弾。
結構な入りで、「椿姫」人気をうかがわせる。
前回同様の2階席からはオーケストラほぼ全体が見渡せた。
非常灯まで消灯された場内、幕は第1幕前奏曲後半で開いた。
半円形にそそり立つ白い壁は一昨年のザルツブルクの映像を思わせる。
舞台には白いスツールがやはり半円形に並んでいる。
右端には男爵から金を渡されるヴィオレッタ。
演出はヴィオレッタが高級娼婦であることを前奏曲のうちに知らしめる。
続く夜会のシーンで彼女が沢山に囲まれて歌うシーンは皆無といってよく、
周囲の人々のほとんどは常に彼女に距離を置いているように見える。
第2幕終結部、金を叩きつけられ気絶せんばかりのヴィオレッタ。
この演出では誰一人彼女を支えようとするものはいない。
自分を悔いるアルフレードにヴィオレッタがすがっていくが、
アルフレードは何もできず、彼女は自らその場を離れ一人取り残される。
第3幕の死の場面でも舞台上の他の4人とは離れた空間に一人出て行き倒れる。
(必然的にアルフレードの最後の叫びはカットされることになった。)
高級娼婦=道を踏み外した女の報われない真実の愛へのとまどいと孤独を表出しようということか。
興味深いのは第1幕最後、アルフレードが舞台に入ってきて二人が抱き合って幕が閉じる。
二人が倒れこむのは長い半円形のスツールの右端、
開幕で男爵と彼女が抱き合っていた(だろう)場所だったりする。
こうした演出だが、孤独な立ち位置の確保のためか?
ヴィオレッタが時折意味が不明な移動しているように思えた。
特にフィナーレでは(記憶では)たぶんヴィオレッタだけが、
大きな柱の影を歩いて右往左往するのは疑問が残った。
舞台装置は巡業向けではないのだろうが実に簡素。
各幕にはものは違うが椅子あるいはテーブルが一つあるだけというもの。
ザルツブルクと違う点は、照明をやや暗めにして円形の壁の何処かを開けて光を差し込ませること。
象徴的といえば褒め言葉だし、けなそうと思えば安っぽいアイディアと言える。
歌手はそれぞれ強力な個性は感じられないが、大きな不満は感じなかった。
ヴィオレッタは、若すぎずおばさん過ぎず、役に合った声質の持ち主。
技巧的な部分では音をひきづるような歌い方が気になったが、叙情的な部分では美しい歌を聴かせた。
アンサンブルでは男声陣に押され気味だが、全曲ほぼ出ずっぱりなのだからたいしたものである。
ジェルモン親子は共に十分な声量で立派、
しかしアルフレードにはもう少し若々しい勢いが、
ジョルジュにはもう少し老いた雰囲気が欲しかった。
立派といえばこの日一番立派な声は第3幕のグッドウィル医師。
オケはけして一級品とは言えない。基本的にはざらざらごつごつとした感触。
それでもフィナーレのオーボエ、ヴァイオリンのソロなど美しい聴かせどころもあった。
指揮者はカーテンコールでは実に愛想のいいおじさん。
こちらも強烈な個性はないが、明確な指揮ぶりは全体をそつなくまとめていた。
終演21:20
主なキャスト
ヴィオレッタ:アンナ・トドロヴァ(たぶん美人)
アルフレード:トマーシュ・チェルニー(いい声よ!)
ジョルジョ:マルティン・バールタ(もう少し貫禄があれば・・・)
アンニーナ:ダナ・コクレソヴァー(献身的な役を好演)
指揮:エンリコ・ドヴィコ(そつのない、バランスの良い指揮ぶり)
演出:アルノー・ベルナール(欠席)
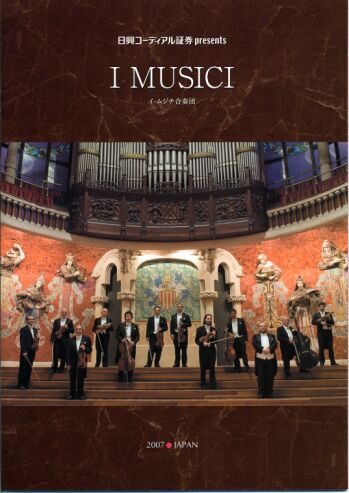 1973年秋、小学5年生で初めて聴いた生のクラシック。
1973年秋、小学5年生で初めて聴いた生のクラシック。
それがイ・ムジチ合奏団。
今度は自分が小学5年の息子を連れて聴きにいく。
某証券会社の協賛があり、顧客にCDとプログラムのおみやげが配られていた。
そのせいでもないだろうが、聴衆の年齢層が以上に高い。
10代の聴き手は100人に満たないのではないか?
1曲目は34年前と同じ、モーツァルトのK.525。
いきなり最初のGの主和音が実に豊かに尾を引く。
そういえばPMFでたくさん聴いたが、Kitaraではムーティだけだった。
コンサート・マスターのサルヴァトーレの艶やかな響きが演奏をリードして行く。
ただこの人、アップ・ボウの弾き方がややぞんざいで音にムラが生じるのが目立つ。
全体的にはいかにもイタリアでございますという様な、強いカンタービレは聴かれない。
ちょっとしゃれた感じで小気味よいフィナーレが楽しかった。
オーケストラのコンサートでなかなか聴けないレスピーギが2曲目。
聴きなれたカラヤンの分厚いサウンドとは当然違っていて、
曲本来の古風なスタイルや内声の動きの美しさが引き立つ。
盛りだくさんの前半の3曲目はこれも珍しいパガニーニ。
「ヴェネツィアの謝肉祭」はおなじみのテーマによる超絶技巧の変奏曲。
第1ヴァイオリンのサブに座っていたアンセルミがセンターに立って弾いた。
本来ソロの人ではないから強烈な個性やうまさが出ないのはしょうがない。
むしろもう少し伴奏がしっかりとしていればソロが引き立ったと思われた。
後半は言うまでもない「四季」。
全体としてはサルヴァトーレの艶やかな響きがものをいう。
慣れた曲の故か、アップ・ボウ音のムラもやや収まったが、
中間楽章では加えられた装飾音はちょっと不確かで、
工夫に乏しい、宙ぶらりんな感じがした。
全体としてイ・ムジチらしい、オーソドックスなスタイルで曲は進む。
慣れ親しんだ昔の録音での力強さ、輝かしさは控えめで、
「春」や「秋」の第3楽章のトゥッティで聴かれる温かみのある響きに魅せられた。
今風のはっとさせるような仕掛けは皆無と言っていい。
それだけに細かい傷が目立つのも確かで、この点では辛い評価も出そうだ。
「冬」の終楽章は見事なアンサンブル、終わり良ければなんとやらで満足の40分。
アンコールはなんと3曲。
ロッシーニ:ボレロ
山田耕作:赤とんぼ
ヴィヴァルディ:「コンカ」より
童謡含めた3曲のアンコールに多くの紳士淑女達が席を立ち拍手を送った。
前半だけで1時間のコンサートは終演21:20
帰りの車中では、「アイネ・クライネ...」をリクエスト。
「迫力はなかったけれど、知っている曲がたくさんあった。」
「ここで、歌いそうになってやばかった」
とのこと。
 開演の3時になってもほとんど無人のステージ。
開演の3時になってもほとんど無人のステージ。
2日目とはいえ、記念すべき公演、
FM生中継もあるらしいし、曲が曲である。
聴く方以上に演奏する側の方が、気合が入っていよう。
実際大変に熱気をはらんだステージとなった。
特筆すべきは全体をよく見通せるバランスのよい響き。
この曲は時に暴力的なまでの強奏をオーケストラに要求するが、
この日の演奏はそんな場面が混雑とした騒音となることは皆無。
今の札響の充実と開館10年目のKitaraの結びつきの賜物だろう。
もちろん具体的に細かい注文を言えば多々浮かんでこよう。
尾高さんの基本的にジェントルなスタイルではマーラーには「毒」が薄い。
第1、第2楽章のコーダの味気なさなどはその典型だろう。
終楽章大詰めのピウ・モッソのテンポの速さも気になった。
それにオケの地力の問題。
管楽器の不安定さは毎度気になるが、
通常よりも多くエキストラが加わるためか、
さすがの弦楽器も求心力の維持がむずかしいのを感じるシーンがあった。
第1楽章再現部直前、低弦のコル・レーニョの鋭さは特に印象に残ったが、
第1楽章の第2主題の音程の悪さはおよそ札響らしくないし、
随所でマーラーが使うグリッサンドのあいまいさも気になった。
メゾ・ソプラノのレンメルトは美しく繊細な声を聴かせたが、
4楽章後半あたりはもう少し芯の強さがほしかった。
ソプラノの松田はソプラノらしい華に欠け、叫びがちのところもあって水準に届かなかった。
合唱団は札幌の3合唱団の合同。
冒頭のアカペラでは発音が妙に素人っぽいのが気になったが、
全体のできはオケ同様に見事なバランスで聴かせた。
さすがに終結合唱ではオケの力演の響きに埋もれがちだったのは残念。
いずれも総体の充実からは大きな傷ではない。
壮麗なクライマックスを築いた尾高&札響に新たな黄金期の到来を予感したといったら褒めすぎか。
全曲80分ほど、この「復活」という音楽。
聴き手はもちろんだが、演奏する側にとっても息をつかせぬくらいの密度の高さと、
強力な推進力を持っているように思われた。
終演16:40
コンサートインデックスへ
トップページへ
 何とか月初の仕事を片付け、駆けつけた「フィガロの結婚」!
何とか月初の仕事を片付け、駆けつけた「フィガロの結婚」!
「アイーダ」と共にガキのころから知っていた「歌劇」である。
25年ほど昔、学生による教育大オペラの「フィガロ」が、
我がオペラ初体験となったのを思うと感慨深い演目、ホールである。
ダブルキャストの二日目ということで、「格落ち」かなと思ったが、
音楽的には大変充実した文句のないものだった。
一番の殊勲は客演の二人の男声主役。
フィガロの星野、伯爵の宮本ともその第一声から存在感十分。
全体にわたって安定した歌唱で舞台を支えた。
特に1、3幕のレチタティーヴォでは見事なつばぜり合いを聴かせた。
ただ星野は後半やや疲れたか声の伸びが落ちたか・・・。
女声陣は客演の二人を誠実で端正な歌唱で迎えた。
スザンナの安田は最初はフィガロに比べて声が前に届かず、
伯爵夫人の高坂は最初のアリアが音程が安定せずと
それぞれ不安の立ち上がりだったが、次第に調子を上げた。
特に第3、4幕のふたりのアリアと二重唱はその端正な美しさで
客演の二人を越え、この日一番の聴き物だった。
ケルビーノの新関も二つのアリアを押しは弱いが端正な歌唱でこなし、
第2幕の感情表現ではアリア以上に劇的でその存在感を示した。
その他歌い手ではマルツェリーナの菅原が立派な声でその存在感を示した。
特に第4幕ではめったに聴けないアリアを歌うのでは?と思わせるほどの充実ぶりだった。
ただしその相手役バルトロは第1幕でのアリアもカットされ精彩を欠いた。
オケは札響。ライン・ドイツ・オペラでの経歴を持つ児玉宏がチェンバロを弾きながらの指揮。
きびきびとした速めのテンポを基調としながら、ここ一番でたっぷりと歌わせるのも忘れない。
第2、4幕のフィナーレを音楽的に破綻無く安定して演奏した手腕は大いに評価されよう。
札響は全曲にわたり立派なアンサンブルを聴かせた。
ただ、3、4幕で声をマスクしかねない目立ちたがりのオーボエは
相変わらずの札響の問題点露呈といったところか・・・。
音楽面の充実とは別に、舞台演出の部分では素人の自分にも疑問が多い。
三原色を基調にシンプルで広い舞台の三分の一ほどがメインのコンパクトな装置はよいが、
アリアで周囲を暗くし、スポットライト(しかも色つき)を当てる安っぽい演出には閉口した。
最初のフィガロのアリアで格子を思わせるスポットライトを使ったのには身構えたが、
その後の照明の使い方には私には全く必然性のないものに思われた。
第1幕のフィガロやケルビーノのソロに青や緑のライトがなぜ必要なのだろう?
ソロ以外でも第3幕後半から第4幕にかけての群集の扱い方も整理されておらず、
明確な意味付けが感じられなかった。
意味付けという点では、終幕で伯爵夫妻をセンターに配したのだが、
このふたりの和解をテーマにするのならもっと先の幕での演出にそれなりの主張があるべきだろう。
この日の歌手たちはそんな意図に十分応える力を持っていたと思われるだけに残念。
今流行りの字幕スーパーが使われ、大変凝った訳詞が使われた。
今風の口語体を使う一方で普段使わないような画数の多い熟語も多用され、
面白い試みだが、舞台とのシンクロを含め将来へより完成度の高いものが望まれよう。
いろいろ文句も連ねたが、先に述べたように音楽面の充実度は見事。
女声陣の"ah tutti"の一瞬の響きに感涙物の公演だった。
終演17:15
来年は山下一史を迎え「カルメン」!
ぜひ行きたいが2月2日というスケジュールは今回以上にむずかしい・・・。
 「マタイ受難曲」、宗教を超えて感動を与える音楽史上最高の作品!
「マタイ受難曲」、宗教を超えて感動を与える音楽史上最高の作品!
ネットで使われたこの宣伝文句、渡されたプログラムの冒頭も飾っていた。
「コーロ・ファーチレ」失礼なことにはじめて聴いた名前である。
しかし「これまで,モンテヴェルディ「聖母マリアの夕べの祈り」,
プーランク「スタバトマーテル」,メンデルスゾーン「エリア」
(いずれも道内初演)」というからすごいではないか!
オーケストラもあわせてアマチュアの愛好家たちである。
細かい「アラ」を見つけるのは難しくはない。
しかし「マタイ受難曲」という懐の大きな音楽は、
いかなるアプローチも受け入れてくれる。
この日の指揮者、加納氏の解釈は、虚飾を廃したイン・テンポ。
90人ほどの合唱は十分な声量を示した。
第1部の両端のコラール・ファンタジーで合唱とオケのバランスが
今ひとつだったのが残念だが、
随所でのコラールの響きのバランスのよさは立派なものだった。
群集の合唱でここ一番のキー・ワードが明確に聴こえたし、
終結合唱は美しい響きで全曲を締めくくった。
ソロではなんといっても鈴木准の福音史家に注目である。
BCJにも参加しているだけあって、その声質はバッハの音楽にふさわしいもの。
若干の音程の不安定さ、荒っぽい歌いまわしが克服されれば、やがて超一級の福音史家となるだろう。
テノールのアリアも歌い、"Geduld"のアリアは一番の聴きものだった。
イエスを歌った則竹は1部後半で疲れたようだったが、終盤イエスの死から最後のアリアは充実していた。
バスの中原は立派な声だが、もう少しキャラクターによる歌い分けがあってもよかった。
女声陣は声の質がはたしてバッハ向きだったかどうか、好みが分かれるだろうが、
第1幕大詰めでの二重唱は素晴らしく美しいものだった。
疑問だったのは児童合唱のポジション。
札幌市内の中学校の合唱部が全体の中心部で陣取ったが、
大人の声とオケにはさまれて埋もれがちだったのは残念、
思い切って一段高いPブロックで歌うのがベターではなかったか?
あと個人的にはレチタティーヴォにはチェンバロの響きが欲しかった。
とはいえ「宗教を超えて感動を与える音楽史上最高の作品!」
その文句を納得させるに十二分なコンサートだった。
終演 18:30
 「木曜日は札響を聴く」1月中旬!その後半?
「木曜日は札響を聴く」1月中旬!その後半? 会場は無料ということもあり?、幅広いようだが平均して
高年齢層の聴き手で9割近い入りとなった。
当家一行など好例である。下から10歳、44歳、70歳!
お父さんががんばって確保したのはCBブロック3列目センター。
そういえば爺様、息子ともに初のCBブロックである。
そのポジションには爺様は特に満足してもらえたようだ。
続いては本日の先出しメインディッシュ?「ドボ8」である。
尾高さんの解釈はあまりテンポをくずさない上品なもの。
それが災いしたのか、オケのテンポの感覚と「ずれ」があるように思われた。
特に第1楽章で楽想の切り替えがうまくいかないもどかしさを感じた。
そんなわけでイン・テンポではすまない中間楽章が出来がよかったように思った。
不調に思われたヴァイオリンが第2楽章では温かく、第3楽章では艶やかな響きを聴かせた。
後半はシュトラウスファミリーの作品。
先週聴いた秋山に比べると、上品な薄口が特徴となろうか、
「こうもり」序曲での細かいテンポの動かし方など秋山の老獪さには及ばない。
しかし「憂いもなく」では、中間部でオケ・メンバーの声も元気がよくて楽しく、
「ウィーンの森の物語」の序奏では珍しい?弦楽八重奏でのツィター・パートが聴けたりと、
例によって熊のようにうろうろしながらのトークをはさんで、楽しめるものだったのは間違いない。
「狩」では、ピストルを3丁も準備して、中間部では空砲にして、
コーダで派手に鳴らそうとしたようだが、音自体がショボイのは残念。
「ドナウ」の後にもトークをはさんで、拍手するのが悪いような上品な「ラデッキー」で締め。
と思ったら「もうアンコールはやりません・・・」とさらにトークでお開きとなった。
コバケン路線を行くとは思えんが、ずいぶん饒舌なこの日の尾高さんであった。
終演21:10
この日の後半の曲目
「こうもり」序曲、「憂いもなく」、「ピチカート・ポルカ」、「ウィーンの森の物語」、
「狩」、「美しく青きドナウ」、「ラデツキー行進曲」
 新年「一発目」(私じゃない!秋山さんの言葉!)は
新年「一発目」(私じゃない!秋山さんの言葉!)は 第2楽章はさすがに勢いがついてきて、満足いくレベルになったが、
やはりトゥッティでの響きがどうも美しくない。
また多用されるヴァイオリンの重音がスカッとしないのである。
これでオルガンの響きがドカーンとくればまたうれしいのだけれど、
第1楽章では上品で感心したルロワは、第2楽章では物足りない。
「ブラヴォー」だって?冗談じゃない!
本当の札響はこんなんじゃない、もっとすごいはずだと思う演奏だった。
後半は「ニューイヤー」にふさわしい?ウィンナ・ワルツ&オッフェンバック。
秋山の指揮はやや粘っこいが、堂々たるシンフォニックスタイル。
特に二つの序曲や「春の声」でのテンポの動かし方など実にはまっている。
ここまでやればサン=サーンスの練習はおろそかになるだろうとひねくれ者には思われた。
実際、「チク・タク・ポルカ」や「とんぼ」といった「慣れていないだろう」曲で、
オケの響きが不安定になるのはいただけない。
とはいえオッフェンバックでは予想通り大平さんの素敵なソロが聴けたし、
新年にふさわしく音楽を楽しめる雰囲気だったのは間違いない。
「ドナウ」の後は当然父の行進曲。
なんとさらにその後秋山&札響からのサプライズはルロワを再登場させての「威風堂々」第1番。
やはり響きは濁りがちだが、うれしい音楽好きへの「お年玉」だった。
ハードスケジュールが続くが、ぜひとも常に定期演奏会のレベルを維持していただきたい。
がんばれ!札響
終演21:10
この日の後半の曲目
「こうもり」序曲、「チク・タク・ポルカ」、「春の声」、「天国と地獄」序曲、
「トリッチ・トラッチ・ポルカ」、「とんぼ」、「美しく青きドナウ」、「ラデツキー行進曲」、
「威風堂々」第1番