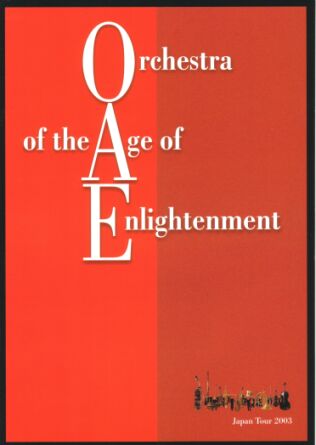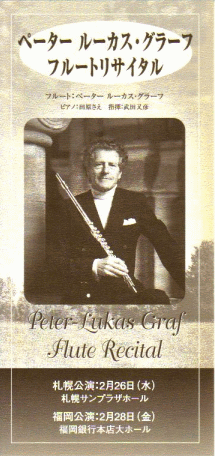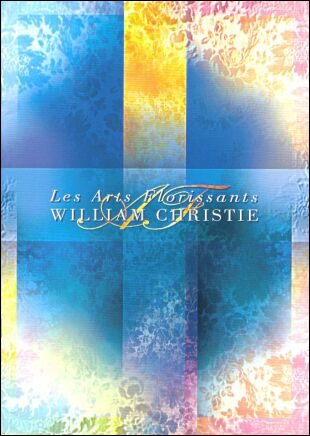2003年のコンサート
2003年10月31日 札幌コンサートホール エイジ・オブ・エンライトメント
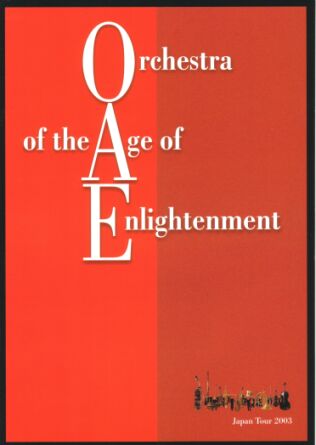
今年はPMF以外はお金をはらってコンサートへ行ってないような気がする。
今日は地元紙のプレゼント。ただし子供同伴(-_-;)
10列目の特等席に5組ほどの親子連れが陣取る。
それにしても1,000人入っているのか?。 Pブロックをぬいて1,800。
あまりにも寂しすぎる。
弦楽器は6,6,4,3,2、もちろん両翼配置のヴァイオリン。
コンサート・ミストレスがやや高い椅子に座ってリードする。
オール・モーツァルトの最初はK.525。
チューニングが悪いのか、
古楽器特有の響きににごりが感じられる。
早めのテンポの設定には問題はないのだけれど、 第1楽章では
ダイナミクスをやたらいじるので
音楽に落ち着きがない。
第2楽章ではヴァイオリンが美しかったし、
第3楽章トリオではソロと、トゥッティを交代させたりと、
個々のシーンでは印象に残るのだけれど、
総合点では今ひとつ。
全曲すべてのリピートを実行していた。
ヴァイオリン協奏曲第1番、第3番
ムローヴァは黒のドレス、オケの方を向くとぐっと背中があいている。
驚いたのはその音、10列目という場所もよかったのか、実に美しく、
よく通る音。 これほど細部までくっきりと音が自分に届いてくるのは、
PMFでの後藤みどり以来だろうか、Kitaraでは初体験である。
ピリオド奏法も取り入れ、時にはアーノンクール張りの音の扱いも聴かせるが、
押し出しはきつくなく、アンチ・古楽器派のモーツァルトのイメージを壊すこともないだろう。
もう少し「毒」があってもよかったかもしれない。
オケも管楽器が加わり予想以上に色彩豊か。ただオーボエの音程の不安定なのが時折目だった。
ただし休憩をはさんだ第3番は、ちょっと急ぎすぎた感じで雑な仕上がりだったのが残念。
ムローヴァは自分としてはちょっとぎすぎすしたイメージの女性だったが、終演後の笑顔が実にチャーミング。
最後は交響曲40番、もちろんクラリネットなし。
この日一番の聴き物で、第1楽章は主題もさりげなくて、どうということもなかったのだが、
速めのテンポの第2楽章から集中度が増し、峻烈な表現を見せたメヌエット、熱気あふれる終楽章で締めくくり、
聴衆の反応も大きかった。ただしこの曲ではリピートをほとんど実行せず、終楽章は前後半ともノーリピート。
本来大交響曲となるこの曲が、演奏の表現とは逆に尻つぼみに終わる形となり、最初に聴いたK.525と
曲の構成への解釈の点で整合性を欠くように思えた。貸館時間の関係だろうか?
アンコールにはK.201のフィナーレ。これも残念ながらノー・リピート。
けれどもアンコールだから許そう。終演21:10。
コンサートインデックスへ
トップページへ
2003年05月29日 札幌コンサートホール ビシュコフ指揮ケルン放送響

またまたFMアップルのプレゼントでチケットが大当たり!
チケットが家に届いたのはなんと前日の朝!。
しかもペアだよ、これ(^^;、S席15,000円なり×2だよ!!
急遽の誘いに応じてくれたI嬢がKitaraに姿を見せたのは開演ぎりぎり。
チケットの半券が切られたのとほぼ同時に開演のベル。
ホールに入って驚いたのは入りの悪さ、6割程度かしら。
席に着くと即オケのメンバーが登場、となりでは息を切らしている。
前半は庄司紗矢香を独奏にブルッフのコンチェルト。
赤ながら清楚なイメージのドレスで才媛は登場。
最初の第一音から演奏の内容に期待ができる響き。
こうした感触というのはそうあるわけではない。
低音から高音までむらのない、美しく深みのある音、重音のバランスのよさ。
年齢、あるいは性別を引き合いにしてはいけない、とにかく大変な大物である。
ただ後半のための大編成のセッティングの中、やや引っ込んだ位置で弾くことになり、
16型のオケにはさすがに音量的にのまれてしまう事があった。
ビシュコフのサポートはオケに任せた感じで、トゥッティでは響きが雑になる感があった。
アンコールにレーガーの作品。
まさしく水を打ったような静けさを作り出した聴き手の集中の中で鳴り響いた。
後半はショスタコーヴィチの「レニングラード」、プロによる北海道初演とのこと。
レニングラード生まれのビシュコフの血とケルンのオケの機能が結びついた名演が期待された。
個人的感想としてはその期待はオケの高い能力によって半ばは満たされたといったところか。
弦楽器群の質感、バランスはすばらしく、冒頭主題をはじめ随所で見事な合奏を聴かせた。
特にヴァイオリンの音色、ビブラートの均一感は見事、これは1月余りで聴くことになるPMFOには
残念ながら絶対に期待できないもの、長年のアンサンブルの賜物である。
管楽器は木管楽器がどのパートも見事なソロを聴かせた。
驚いたのはファゴット。リードも替えるのだろうが、
朗々たるソロがホールに響いた。
ただし金管楽器を含めた全体のアンサンブルでは、完璧というに今ひとつ整理が行き届いていない感じがした。
ビシュコフの指揮は、熱のこもったもので、ダイナミクスは作曲家の指示にそってはっきりと段階付けられる一方、
フィナーレ大詰めをはじめ、随所でテンポの扱いにはかなり自由な変化を付けているように思われた。
ただしそれが即興的なのか、今ひとつオケが付いて行けずにぴたりと決まらないもどかしさもあった。
と文句をつけながらも曲が曲だけに、熱演指揮者と、高機能オケによる演奏は、オーケストラ音楽の醍醐味を
十分に堪能させてくれたことには違いない。
演奏後ほとんど全員がパートごとに立たされた。一番の喝采を受けたのはもちろん!小太鼓奏者。
最初のうちはどこで叩いているのかわからないほどの小さなアクション、しかし恐ろしいほど明晰な音で
チチン・ブイ・ブイを支えた。二番手は先に述べたファゴット。
喝采といえば少ないながらこの日の聴衆の反応は実に熱心。一度始まった拍手は途中静まることなく、
高いテンションでステージに賛辞を送り続けた。
大曲にアンコールは必要なし。終演21:20。
コンサートインデックスへ
トップページへ
2003年02月26日 札幌サンプラザホール
ペーター ルーカス・グラーフ フルートリサイタル
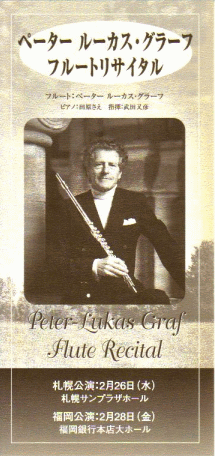
FMアップルのプレゼントでチケットが大当たり!
というわけで急遽予定に入った2月二つ目のコンサート。
自分が子供のころにはメジャーであった人でレコードもあったが、
正直にいってその録音を聴いた記憶がほとんどなかったりする。
印象としては、明るく、抜けたような音ではなく、骨太、厚く、暗めの音色、
フレーズはていねいに念を押すように刻んでゆく感じ。
ロングトーンで時折音がぶれるような感がするのはさすがに年齢のせいか?
しかし積み重ねられるように進む音楽に次第に引き込まれていった。
前半はソナタを3曲、最初のビンシはバッハとほぼ同年代の人。
歌謡的な旋律は、ややフレーズが短く整理されすぎて音楽の流れが
悪くなる事が時折あった。続いてはバッハ、先に述べた特徴が生きるのは
やはりバッハの音楽だろう。実に明確、ほどよい緊張感をはらんだ音楽。
3つ目のプロコフィエフはさらに力強さも加わり、この日の白眉となった。
ここまで1時間弱、曲の合間はほとんど休みはなく、74歳という事を全く
感じさせないステージとなった。ブラスバンド所属なのだろう。制服姿が多く
見られる聴衆の集中力は楽章ごとに高まっていく。休憩は10分。
後半はショー・ピースとまではいかないが、ソナタではない作品が4つ、
中では福島和夫の「冥」という作品が日本的な曲想の中で、いろいろな
奏法が試されており聴き手の感心を集めた。
ただルーセルやフォーレなどはもう少しくつろいだ感じがほしかったような気もする。
最後にパガニーニのおなじみの主題によるカプリース。これは自らの編曲でもありノリのいい演奏。
アンコールはそれまでと同様、あまり休まずに4曲、締めの二つはバッハ。
終演まで技術的に安定した演奏で、聴き手を掴んで放さない。
伴奏はソロとのバランスに十分に心を配ったもの、しかし今ひとつの音楽への鋭い切り込みが欲しかった。
終演、21:05。
コンサートインデックスへ
トップページへ
2003年02月14日 札幌コンサートホール クリスティ指揮レザール・フロリサン
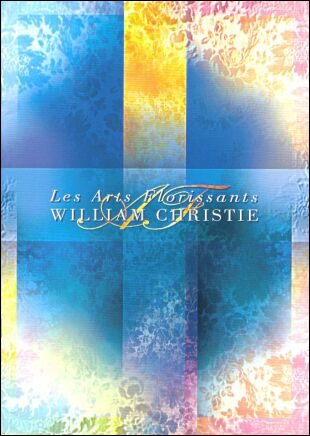
今年初のKitaraは声楽物となりました。
私自身は何の知識もないのですが、2ちゃんねるで来日記念スレッドが
立つくらいなので、古楽ファンは注目の団体なのでしょう。
メンバー表にヒロ・クロサキの名前を見つけて「あー」と思うのでした。
曲目は「メサイア」、以前にPMFで簡略ヴァージョンで熱気あふれた
演奏を聴いたことがありました。
陣取ったのはCCブロック最前列でちょっと遠い感じです。
古楽とはいえ金管、打楽器も加わる編成ですから、椅子の数は意外と
多いです。第1ヴァイオリンは6人、チェロは4人、合唱は25人です。
声楽はソプラノは女性、アルトはカウンター・テナーが担当しました。
ソプラノ独唱はふたり、曲の内容ににより振り分けていたようです。
演奏自体は、大掴みと言っていいのか、細かい部分のアンサンブルには
とらわれず、速めのテンポで曲間を短くとってぐいぐいと曲が進んでいく感じ
です。その熱気をもった曲の進め方はトスカニーニ風でもあります。
オケは実に整備された響きですが、低音は人数のわりに控えめで、
重心が軽い感じがしました。注目は鍵盤楽器。ハープシコードとオルガンを
一人で弾き分けていましたが、曲間が短い解釈だけにその切り替えの
忙しさは、そのダイナミックな弾き方と合わせてこの日一番の見ものでした。
合唱は声の量、質ともにたいへん高い水準ながら、縦線のそろいは今ひとつの感がありました。
25人が1列に並んだのですが、ソプラノの人数が多い分、各声部の音の広がり方にバランスの悪さを感じました。
70年代後半生まれの人もいる独唱陣はいずれも誠実な、丁寧な歌でした。
しかしそれ以上のものを多く聴かせてはもらえなかったというのも事実です。
ソプラノのディンマンは魅力的な声で、モーツァルトあたりを聴いてみたいと思わせました。
もう一人のソプラノ、イムも可憐で魅力的ではありますが、メリスマ的な歌唱にはやや硬さがのこります。
1979年生まれのカウンターテナーデュモーは押し出し不足ですが、不安のない歌唱。
テノールのベイトンはやや力みが感じられたのが残念。バスのゲーは全体の色彩にあわせたのか、
重心の高い感じの歌唱でした。
細かい部分に文句をつけるときりがないのですが、全体としてはクリスティのダイナミックな曲の運びに
のせられて、全曲退屈することなく聴けたのは間違いありません。
なんとアンコールにラモーの「優雅なインドの国々」から華の四重唱。 終演、21:30。
コンサートインデックスへ
トップページへ
2003年01月05日 札幌コンサートホール ウィーン・リング・アンサンブル
今年最初のコンサートはウィーン・リング・アンサンブルです。
・・・というはずだったのですが、しっかり忘れてしまいました。
今まで2回夕張まで車を走らせて聴きにいっていたのですが、
やっと札幌にきたというのにまんまとやってしまいました。
気がついたときには開演30分後、どう考えても自宅からは間に合いません。
PMFで待ってるよ〜
コンサートインデックスへ
トップページへ